社員インタビューstaff interview
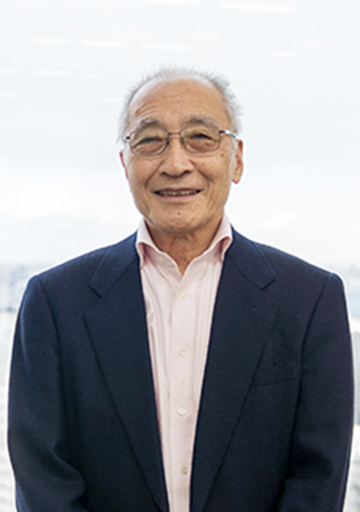
- 信頼性保証本部
- 長年、内資系製薬企業で製剤、特にドラッグデリバリーシステムの研究に従事。その後、複数の大学で教鞭をとり、現在もLTLファーマに勤務しながら、大学の客員教授としてベンチャー企業との共同研究に取り組んでいる。LTLファーマの設立に携わる。

- 流通管理部
- 2020年LTLファーマに入社。取扱領域の異なる複数の製薬企業と製造委託会社の両事業にてサプライチェーン業務に従事した経験を活かし、入社以降は生産管理、在庫管理、流通管理と、幅広い業務に従事している。

- 薬事部
- 大学卒業後に入社した製薬企業では、18年間、製剤設計の研究に従事した経験を持つ。その後、他社の薬事部で勤務の後、2020年7月LTLファーマに入社。薬事におけるキャリア形成を目指している。

- 学術研修部
- 外資系製薬企業にて34年間、営業職、営業マネジメント職、企画職を経験。業界経験・知識を活かし、教育研修に留まることなく、医療機関からの問い合わせ対応管理・サポート、学術資材の作成・整備、MR活動において必要な情報の整理と発信等、幅広い業務に従事している。
PAGE TOP